「特効薬はありません」ひきこもりの家族に私たちはどう接すればいいのか
仕事に就かず、外出もせず、何年も自分の部屋に閉じこもったまま……そうした状態で日々を過ごす「ひきこもり」が全国に115万人存在するという驚愕のデータが厚生労働省から発表された。
政府も対策に躍起になっている。しかし、ひきこもりになったきっかけが1人ひとり異なるだけに、全ての人に対して万能な解決策は存在しない。
対策を推し進める一方で新たに「8050問題」が発生したり、東京都練馬区でひきこもりの長男を元農林水産省事務次官が殺害するという痛ましい事件が起こっていたりするのが実情だ。
そんなひきこもりについて、私たちは実際のところどの程度理解しているのだろうか。ひきこもりの治療に携ること10年、精神科医として現場で蓄積したノウハウをまとめた1冊『 改訂版 社会的ひきこもり 』からひきこもりに対する正しい知識、そして対処の仕方を紹介する。
◇◇◇
「特効薬」はない

社会的ひきこもり事例の治療に際して、まず確実にいえることは、相談が持ち込まれた時には、状況がかなりこじれてしまっているということです。いったんこじれてしまった場合は、もはや周囲がどのように働きかけても、好ましい変化は起こりにくくなっています。それどころか、働きかけること自体が、本人を追いつめる結果になってしまいがちです。
ですから、まず家族が理解しなければならないのは、このような状態から短期間で立ち直らせる特効薬はないということです。ともかく、じっくりと腰を据えてとりくむほかはない。しばしば、家族や治療者の励ましや適切なアドヴァイスによって、一気に立ち直ったかのような事例が紹介されます。しかし、私の経験では、このような「美談」は、ありえないとまではいいませんが、まったく例外的なものです。そうでなければ、そうした励ましの効果は一過性のことが多い気がします。一般的にひきこもり状態からの立ち直りには、短くても半年、平均して2〜3年以上の時間が必要となります。もちろん、これはあくまでも、適切な対応がなされていた場合の話です。
ひきこもりをはじめとする思春期の問題に対しては、「周囲がどれだけ待つことができるか」が、その後の経過を大きく左右します。したがって家族の基本的な構えとしては、「本人の人格的な成熟を、ゆっくり伴走しながら待ち続ける」ことが必要となります。「焦り」は何ももたらしません。むしろ、慢性的な焦りこそが「ひきこもりシステム」を強化してしまいます。
相手を信じる大切さ
希望を捨てずに待つという姿勢は、それ自体が本人に好ましい影響をもたらします。「待つ」ということはまた、冷静に構えるということでもあります。本人の言動や、わずかな状態の変化に一喜一憂せず、長期的展望を持ってどっしりと構えること。家族がまず専門家に相談すべきなのは、こうした展望をしっかりと確保するためでもあります。つまり「ひきこもりは簡単には治らない」ということと、「ねばり強く十分に対応を続ければ、必ず改善する」ということの二点を、深く理解するためです。治療のなかでときどき起こることですが、本人がある日突然、理由もなく活動的になったり、意欲的になったりすることがあります。こんな場合に「やっと目を覚ましてくれた」などと、手放しで歓迎すべきではありません。思春期に起こる急激な変化は、しばしば精神疾患のはじまりを意味していることが多いからです。一見よい変化にみえたとしても、理由や方向がはっきりしないものであるなら、むしろ十分に注意しなければなりません。
もちろん、ただ待てばよいというものでもありません。変化を待ち受けつつも、水面下での絶え間ない努力が必要です。家族間の意見調整や、家族だけの治療相談なども欠かせません。そして同時に、本人が症状を通じて何を訴えようとしているかを、しっかりとみきわめることです。いたずらな干渉をひかえて、暖かく見守り続ける姿勢が大切なのです。「手をかけずに目をかけよ」と、むかし先輩に教わったことがありますが、まさにその通りでしょう。
治療における「愛」の難しさ
治療場面ではよく「本人への愛情を大切に」といった「指導」がなされます。しかし私は「愛」というものは非常に難しい言葉であると考えています。「愛」の素晴らしさを否定こそしませんが、それはしばしば「出来事」としての素晴らしさなのであって、治療の手段としてコントロールできるようなものではありません。「愛情を持って接してください」という言葉を、私もいわなかったわけではありませんが、つねに一抹の虚しさを感じていました。
愛情を強要することは、しょせん無理に違いないからです。
しかし、それでは、治療者は愛についてふれるべきではないのでしょうか。それはそれで、うるおいのない治療になりそうな気もします。果たして、愛を強要せずに、しかも愛をそこなわないやり方が可能なものでしょうか。
80年代に人気のあったアメリカの小説家、カート・ヴォネガットの本に、「愛は負けても親切は勝つ」というくだりをみつけて、私はそれを何となく記憶していました。「勝つ」とは何に勝つのだろうな、とか、親切がいつでもよいものとは限らない、といった疑問もあります。しかしそれでも、ここには一面の真実がある。私はこの言葉を、ひきこもりの事例を抱える家族へ、1つの激励の言葉として送りたいと思います。
母と子の密室的な愛情関係
精神分析によれば、「愛」とはそもそも自己愛に由来するものです。人は、自分を愛する以上に、他人を愛することができない。いやできる、と主張する人は、自覚のないナルシシストである。精神分析は、そう教えます。家族に対する愛でも同じことです。むしろ自己愛との区別がいっそうつきにくいという点で、家族愛こそは要注意なのです。それはしばしば相手を所有し、コントロールしたいという欲望につながり、ときには激しい攻撃性の原因にもなります。後にふれる家庭内暴力もまた、「愛」ゆえの産物です。激しい暴力の後で、必死に謝り、思いやりをみせようとする子どもと、そんなわが子を抱きしめ続ける母親。そこにあるのは、距離とコントロールを失った「愛」の、無惨な姿ではないでしょうか。「愛」は、まさに「盲目」であるがゆえに、治療を困難なものとします。そこでは「愛」は「一方的な奉仕」と容易に取り違えられます。極端な例では、治療者の言葉にすら耳を貸さず、むしろ親子の愛を妨害する邪魔者として、治療者のほうが切り捨てられてしまうことすらあります。このような母と子の密室的な愛情関係は、事態をいっそうこじらせ、不安定なものにしてしまいます。このような結びつきは「共生関係」と呼ばれます。親はそれこそ、強い愛情によって、必死に本人の心を鎮めようとします。しかしそのように力めば力むほど、本人の要求や状態に振り回されてしまい、くたくたになってしまうのです。
母親の献身が逆効果になることも
もちろんひきこもっている本人もまた、自分を愛し、必要としてくれる存在を強く求めています。しかし同時に、自分はいつ見捨てられてもおかしくない人間という認識も捨てられずにいます。母親が尽くせば尽くすほど、自分が母親なしではやっていけない、弱い存在であることを思い知らされます。もし母親から見捨てられたら、自分はどうなってしまうかわからない。20代、30代の「少年少女」たちがそのように語るのを、私は何度となく聞いてきました。母親の捨て身の献身は、案に相違して、彼らのこうした恐怖を救うどころか、いっそう強めてしまうのです。
「共依存」の問題
精神医学には「共依存」という言葉があります。もとはアルコール依存症の事例に見出された家族関係を指していますが、現在はもう少し広い意味で使われています。アルコール依存症患者の家族、とりわけ奥さんは、夫の飲酒癖や飲酒時の暴力に、さんざん悩まされています。しかし、そういう関係が長年続いていくうちに、困らされているにもかかわらず、夫から離れることができなくなってしまいます。つまりこの奥さんは、自分の存在価値を「アル中の夫の面倒をみる妻」という役割に見出すようになってしまうのです。こうして夫は世話役である妻に依存し、同時に妻は、表向きは困りながらも、「ダメな夫の世話役」という自己イメージにおぼれていきます。こういう関係を「共依存」と呼ぶのです。ここには「持ちつ持たれつ」といった、安定した相互性はありません。相手を支配し、自分の満足のための道具として利用するという関係であり、それゆえ一方的で不安定なものとなります。
ここで「アル中」を「ひきこもり」におきかえてみましょう。「ひきこもり」事例の母子関係にも、しばしば「共依存」がみられます。したがって親子関係が膠着状態にあると感じられた場合、このような視点から関係を見直してみることも大切です。そこにはたして、「共依存」関係が存在するかどうかを検討してみること。そして、もし存在するなら、母親がそれなしでもやっていけるかどうか、自身に問うてみること。そのような視点に立つだけでも、いびつな関係性を改善する方向がみえてきます。
ついいいなりになってしまう母親も……
母親と「共依存」の関係にある事例は、ほぼ100%、他人の関わりを嫌い、拒否します。その拒否があまりにも激しいので、ついいいなりになってしまう母親も少なくありません。しかし、ここで妥協すべきではありません。親が治療相談に通う意味は、まさにこの点にあります。密室の親子関係に、さしあたり治療者が、社会の代表として楔を打ち込むこと。もちろん最初、本人はひどく嫌がります。自分のことを無関係な他人に話されるのが嫌なのは当然です。時には親が病院に行こうとすると、暴れはじめる事例もあります。しかし、私が関わったケースに関しては、親が毅然として対応すれば、こうした抵抗はそれほど長続きしません。むしろ親が病院に通いはじめてかえって安心したかにみえる事例が多いくらいです。私はそれが、密室の扉が開かれ、親と自分との関係が、はっきり見えてきたことによるのではないかと考えています。
他人という鏡の重要性
社会との一定の関係が成立してはじめて、親の愛情が意味を持つということ。これはどういうことでしょうか。「すべての愛は自己愛である」と、さきほど私は断言しました。これは事実であるかどうかという話よりは、愛というものを分析するには、さしあたりこのように定義するしかない、という約束事のようなものです。しかし、かりにそうであると仮定して、なぜすべての人が自己愛的に、自己中心的にふるまわないのでしょうか。私はそれこそが「社会」の機能であると考えます。つまり、自己愛というものは、それを維持するために必ず、「他人という鏡」を必要とします。他人を愛し、あるいは他人から愛されることによって自己愛を維持することが、もっとも望ましいのです。
しかし、ひきこもり状態にある青年には、このような鏡はありません。あるのは自分の顔しか映し出すことのない、からっぽの鏡だけなのです。このような鏡は、もはや客観的な像を結んでくれません。そこには唐突に「力と可能性に満ちあふれた自分」という万能のイメージが浮かび上がるかと思えば、それは突然かき消えて、今度は「何の価値もない、生きていてもしょうがない人間」という惨めなイメージに打ちのめされる。このように彼らの鏡は、きわめて不安定でいびつな像しか結んでくれません。ようするに自己愛が健全に(ここでは「安定的に」というほどの意味ですが)保たれるためには、家族以外の「他人」の力によって「鏡」を安定させることが必要なのです。
人間は、自己愛なしでは、生きていくことすらできません。自己愛がきちんと機能するには、それが適切に循環できる回路が必要なのです。幼児期までは、それは自分と家族との間を循環するだけで十分でした。しかし思春期以降は事情が違ってきます。事情を変えるもっとも大きな力が「性的欲求」のありようの変化です。そう、思春期以降の自己愛は、異性愛を介在させなければ、うまく機能しません。そして異性愛ばかりは、家族がけっして与えられないものなのです。
「愛」よりも「親切」
ここで述べていることは、けっして理屈で考えたことではありません。私は多くのひきこもりの青年たちが立ち直っていく際に、異性関係が1つの大きな契機となることを、何度も目の当たりにしてきました。逆にいえば、ひきこもり状態を乗り越えられない青年たちにとって、異性関係こそが最大のハードルであることもみてきました。そして異性関係ばかりは、治療によっても与えることができません。そう、ここでも「愛」は、偶発的な出来事としてしか意味を持たないのです。
そして、だからこそ、治療場面では、「愛」に依存すべきではありません。むしろ「愛」を禁欲してでも、ひたすら「親切」を心掛けるべきです。「親切」は、共感なくして成立しませんが、まさにこの「共感」こそがひきこもり事例の求めるものなのです。深く共感しつつ、いたわりの気持ちを持って、「親切」に接してあげること。それこそが、「治療的」態度です。強い愛は、そのぶん攻撃性などの反動を呼びやすい。「親切」には、こうした激しい両価性はありません。知的理解と情緒的共感に立った「親切」な態度こそが、家族に求められる理想的態度です。
青アザや生傷が絶えない10年間……家庭内暴力に困り果てた家族がとった行動とは へ続く
(斎藤 環)




コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
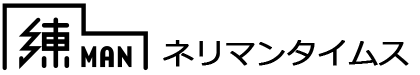
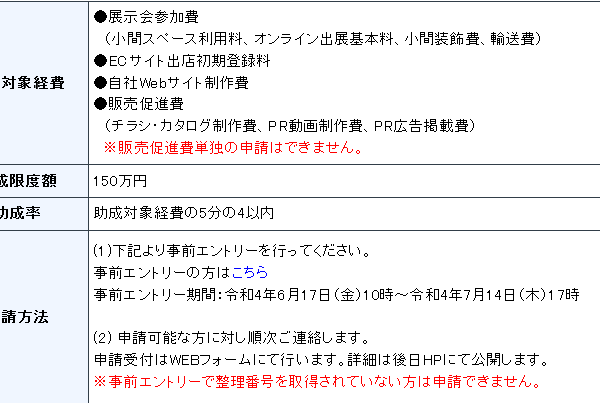
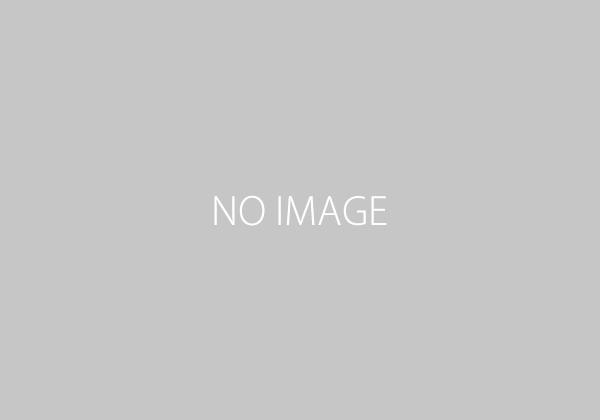





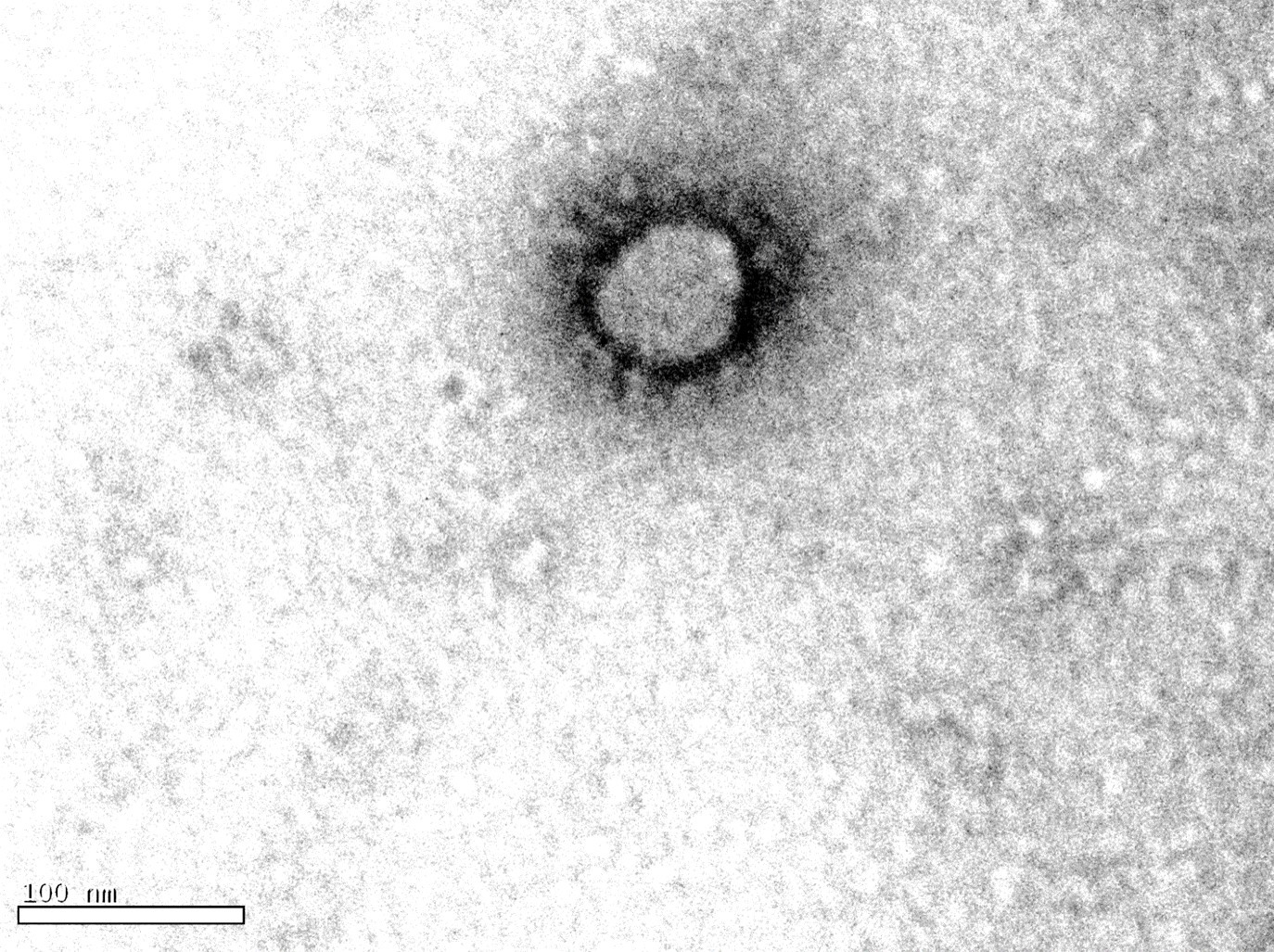

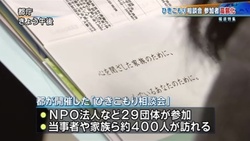
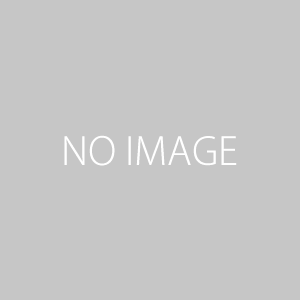
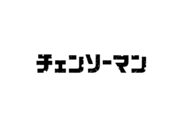
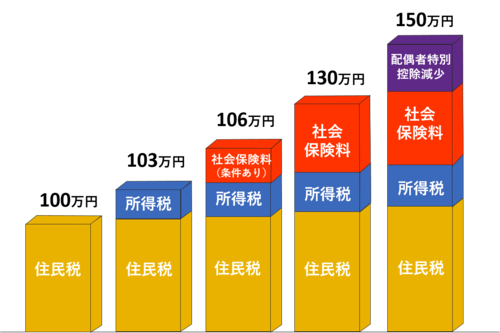







この記事へのコメントはありません。