「ママ、お願いだから来ないで」伝説の名伯楽が“少女バレー教室”で発掘した天才中学生
「言うことを聞くのは当然だ」天才セッター中田久美・誕生前夜、政治介入と戦った女子バレー“伝説の男” から続く
2012年のロンドン五輪で銅メダルに輝いた女子バレーボール日本代表。その監督を務めた眞鍋政義氏(58)が、2016年以来、5年ぶりに日本代表監督に復帰することが決まった。2012年10月22日、眞鍋氏はオンライン会見でこう述べた。
「東京オリンピックで10位という成績にかなりの危機感を抱いている。もし(2024年の)パリ大会に出場できなかったら、バレーボールがマイナーなスポーツになる“緊急事態”であるということで手を挙げさせていただいた」
女子バレーは2021年の東京五輪で、“初の五輪女性監督”中田久美氏(56)が指揮を執ったが、結果は25年ぶりの予選ラウンド敗退。1勝4敗で全12チーム中、10位に終わった。
正式種目となった1964年の東京五輪で、記念すべき最初の金メダルに輝き、「東洋の魔女」と呼ばれた日本女子バレー。だが、その道のりは平坦ではなかった。半世紀に及ぶ女子バレーの激闘の歴史を、歴代選手や監督の肉声をもとに描いたスポーツノンフィクション『日の丸女子バレー』(吉井妙子著・2013年刊)を順次公開する。(全44回の19回。肩書、年齢等は発売当時のまま)
◆◆◆
「天才セッター・中田久美」はいかにして生まれたか
山田はモントリオールで金メダルを獲ったものの、世界の女子バレーは大きく地殻変動しているのを感じ取っていた。もう日ソの時代ではない。スポーツ学校制度が功を奏したキューバが台頭し、高身長の選手を招集し英才教育をしている米国、中国も一挙に力をつけはじめた。ステートアマである共産圏のチームも無視できない存在だ。そう考えた山田は、協会や会社にジュニアの育成を訴えてみたものの受け入れられず、自腹を切って少女バレー教室を始めたのだ。
全国から集まった少女のために家3軒を借り、面倒を見るスタッフも雇った。八王子に広大な“山田の森”を所有する資産家の養子になったことが、このプランを可能にした。
その第2期生が、15歳で全日本のセッターにデビューし、その後“天才セッター”という名をほしいままにした中田久美である。
中田は東京五輪の翌年に、東京・練馬区で生まれた。区立練馬東中学でバレー部に入部したものの、練習で物足りなさを感じていたとき、バレー雑誌で「ロサンゼルス・エンジェルス」の募集広告を目にした。一人っ子の中田は、親に相談したところ猛反対されたが、最後はどうせ受かりっこないと、受験だけは許された。その年は7人募集のところに、全国から1000人近くの応募があった。

中田は人数の多さに諦めかけたが、当時、身長168センチでジャンプ力も飛び抜けていたことから、山田の目に留まった。
バレーに集中するため、中田は寮生活を送らなければならなくなり、中学2年生に進級する前に日立の体育館に近い小平第四中学校に転校した。
「ママ、お願いだから来ないで」の真相
両親はこの転校に大反対だった。しかし中田は親の涙にも動じなかった。
「合格して初めて日立の体育館に足を踏み入れたとき、大変なところに来ちゃったと思ったんです。体育館の壁いっぱいに、モントリオールの金メダリストたちの写真が掲げられていた。子供心に、日立にきた以上は、この人たちが築いてきた伝統を守らなければならないと思った。この時点で、私の覚悟が決まったような気がします。金メダルを獲るためには、すべてのことを捨てなければならないって……」
しかし母の光子は心配のあまり、毎日のように体育館に通い、物陰から娘の姿をそっと見守った。ある日、光子の姿に気がついた中田は、言い放った。
「ママ、お願いだから来ないで。ほかのみんなだってお母さんに会いたいだろうけど、地方の子は会えないんだよ。みんなの気持ちも考えてよ」
それ以来、母は体育館に通わなくなったが、中田は母に来てほしくなかった本当の理由が別にあったと言う。
「私は怒られ役だったので、監督やコーチからたびたび叱咤されていたんです。そんな姿を母に見せたくなかった。母は、私が家を出てから一挙に髪が白くなった。そんな母にこれ以上、辛い思いをさせたくなかったですから」
母への思いを胸に仕舞った中田は、懸命にトス練習に明け暮れた。
「子供が、全日本クラスを操っているんだぜ」
今は取り壊されてしまったが、日立の体育館には一箇所だけ、床が白っぽく変色した場所があった。中田が1人でトス練習を繰り返した場所だ。中田の大量の汗が、床を変色させてしまったのである。だが、床を変色させるほどの汗の量は正直だった。
チームの司令塔であるセッターが一人前になるためには、最低5年の練習が必要とされるが、中田は2年でその技術をマスターし、15歳で早くも全日本入りを果たしたのだ。
中田の才能に目をつけた山田も、これほど早く成長するのは予想外だったらしい。
別のコートで練習していた中田を指差し、白井貴子に嬉しそうに呟いたことがあった。
「おい、あの子を見てみろよ。まだ下の毛も生えていないような子供が、全日本クラスの選手を操っているんだぜ」
天才少女を手に入れた日立は、81年の日本リーグで、ほぼ全日本メンバーをそろえたユニチカを倒し王座に返り咲いた。山田は常々、セッターが一流でない限り一流のチームは作れないと語っていただけに、中田のトス捌きで100種類以上の攻撃パターンを手に入れ、連勝街道をひた走った。日立が王座に返り咲いたとき、山田はこう言ってほくそ笑んだ。
「今後8年間は、日立が負けることはないだろうね。困ったもんだねえ」
「私のトスは(江上)由美さんの作品でもあるんです」
それはとりもなおさず、ロサンゼルス、ソウル五輪と日立主体の全日本を作り、自分が指揮を執(と)るという意思表明でもあった。中田の成長は、それほど大きかった。
だが一方の中田は、自分は決して天才と言われる類の選手ではないと語気を強める。
「すべて反復練習です。ただ、練習のときに一球一球に意識を持ち、身体だけでなく脳ミソにも汗をかいた。すべて練習の成果です。ただ、ロス五輪までのトスは(江上)由美さんに育てられた。由美さんは、世界一の速さを持ったアタッカーだった。由美さんのスピードに負けないよう私も必死でトスを上げた。私のトスは由美さんの作品でもあるんです」
江上は不運な選手だった。モントリオール五輪の年に日立に入社し、白井がいることからセンターにコンバートされ、20歳で日立の主将になったもののモントリオールの中心メンバーがごっそり抜けたため、チームのどん底を味わっている。全日本ではユニチカ中心のメンバーに加わり、脂が乗ってきたモスクワ五輪のときに不参加の憂き目に遭う。
だが、逆風をかき分けてきたからこそ速攻の技術を高め、そのテクニックで中田を育てることが出来たのだ。
江上が言う。
「私の時代は、日立も全日本もセッターが固定されていなかった。そうすると、それぞれのトスに合わせた打ち方を考えなければいけない。色んなセッターの球質に合わせようと努力していたら、知らず知らずのうちに攻撃の幅が広がったのかも……」
《悔しさのあまり、表彰台で…》女子バレー・中田久美が述懐するロス五輪「こんなものいらないと思った」 へ続く
(吉井 妙子/文藝春秋)




コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
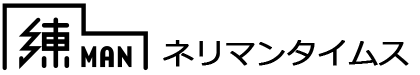
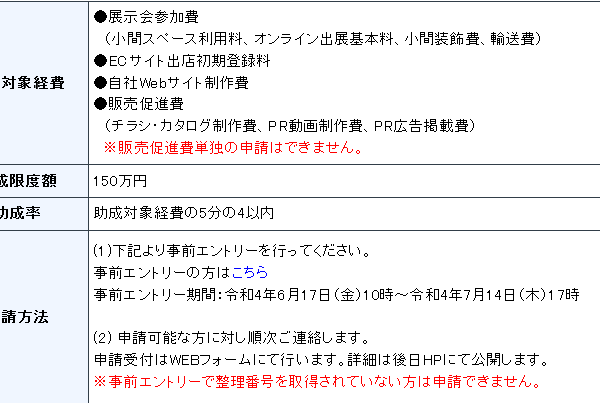
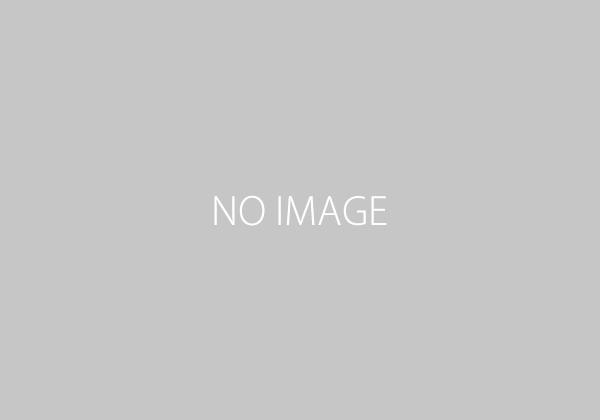





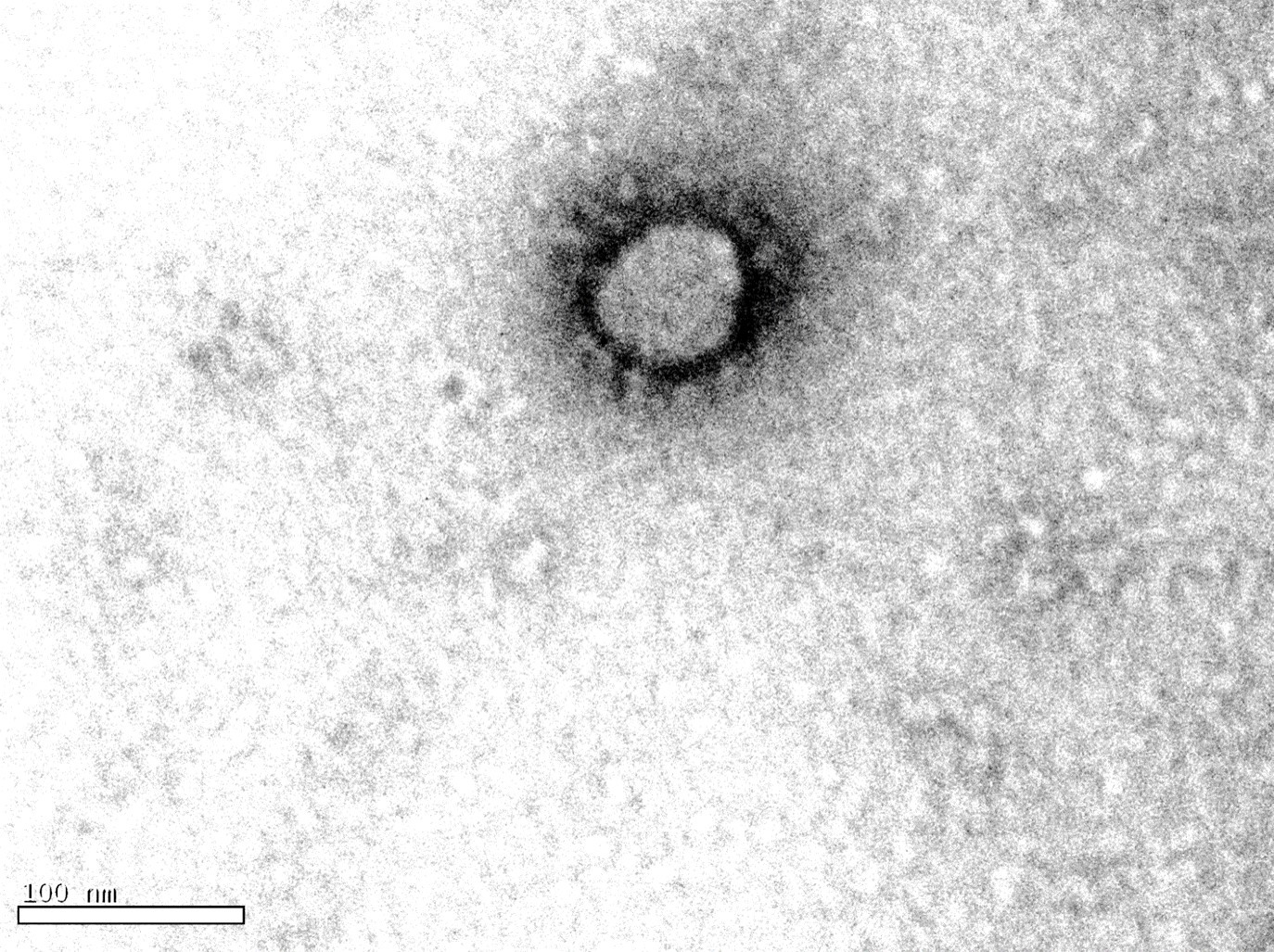
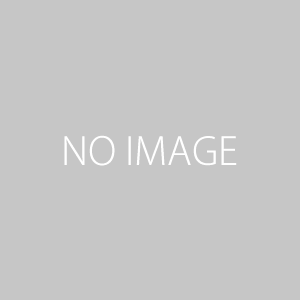










この記事へのコメントはありません。